心筋炎
心筋炎とは
心筋炎(しんきんえん)とは、心臓を構成する筋肉である「心筋」に炎症が起こる病気のことです。炎症によって心臓のポンプ機能が低下すると、血液を全身にうまく送り出せなくなることがあります。その結果、動悸や息切れ、胸の痛みといった様々な症状を引き起こします。多くはウイルス感染が原因とされています。
心臓は主に筋肉でできており、この筋肉が収縮と拡張を繰り返すことで血液を全身に送り出しています。心筋炎は、この心筋に何らかの原因で炎症細胞が集まり、心筋細胞がダメージを受ける状態を指します。ダメージの範囲や程度によって、症状の重さが変わってきます。
急性と慢性、劇症型心筋炎の違い
心筋炎は、経過によって急性と慢性に分けられます。多くは急激に発症する急性心筋炎です。その中でも、特に重篤で命に関わる状態を「劇症型心筋炎」と呼び、急激な循環不全(血のめぐりが悪い状態)に陥ります。一方で、炎症が長期間続く慢性心筋炎は、拡張型心筋症に移行することもあります。
見逃したくない心筋炎の症状
心筋炎の症状は、無症状の軽いものから命に関わる重いものまで幅広いです。初期には風邪とよく似た症状が現れることが多く、見過ごされやすい傾向があります。しかし、その後、胸の痛みや息切れといった心臓に関連する症状が出てくるのが特徴的です。
初期症状
心筋炎の発症前に、発熱や咳、喉の痛み、倦怠感、筋肉痛といった、風邪やインフルエンザによく似た症状が見られることが多くあります。これらの症状が数日から2週間ほど続いた後に、心臓の症状が現れるパターンが一般的です。風邪が長引いていると感じたら注意が必要です。
胸の痛みや圧迫感
心筋炎の代表的な症状の一つが胸の痛みです。締め付けられるような痛みや、チクチクするような痛み、圧迫感など感じ方は人それぞれです。この痛みは、心筋の炎症や、心臓を包む膜(心膜)にまで炎症が及ぶことで生じます。狭心症や心筋梗塞との区別が重要になります。
動悸や息切れ、呼吸困難
心臓のポンプ機能が低下すると、全身に必要な血液を十分に送れなくなります。その結果、軽い運動でも動悸がしたり、息切れがしたりします。症状が進行すると、安静にしていても呼吸が苦しくなることがあります。横になると息苦しさが増す場合は特に注意が必要です。
むくみや倦怠感
心臓の機能低下により、体内の血液循環が悪くなると、足や顔にむくみ(浮腫)が現れることがあります。また、全身に十分な酸素や栄養が供給されなくなるため、強い倦怠感や疲労感を感じることもあります。普段と違うむくみやだるさに気づいたら、受診を検討しましょう。
心筋炎の主な原因
心筋炎を引き起こす原因は様々ですが、最も多いのはウイルス感染です。風邪やインフルエンザ、胃腸炎などを引き起こすウイルスが心筋にまで感染し、炎症を起こすケースが知られています。その他、細菌感染や薬剤、自己免疫の異常などが原因となることもあります。
ウイルスや細菌の感染
コクサッキーウイルスやアデノウイルス、インフルエンザウイルスなどが主な原因ウイルスとして挙げられます。これらのウイルスが体内に入ると、免疫反応が心筋を攻撃してしまうことで発症すると考えられています。ウイルス以外にも、細菌や真菌(カビ)の感染が原因になることもあります。
薬剤やアレルギー反応
特定の薬剤に対するアレルギー反応や副作用として心筋炎が起こることがあります。抗菌薬や抗てんかん薬、抗がん剤など、原因となりうる薬剤は多岐にわたります。薬物治療を開始した後に体調の変化があった場合は、速やかに医師に相談することが重要です。
特定の原因が不明な場合
様々な検査を行っても、心筋炎の原因が特定できないケースも少なくありません。このような場合を「特発性心筋炎」と呼びます。原因が分からない場合でも、症状や心臓の状態に合わせた治療が行われます。自己免疫の異常が関与している可能性も考えられています。
検査・診断方法
胸の痛みや息切れなどの症状で医療機関を受診すると、まず問診や身体診察が行われます。心筋炎が疑われる場合、心電図や血液検査、心エコー検査といった複数の検査を組み合わせて診断を進めます。確定診断のためには、さらに専門的な検査が必要になることもあります。
心電図検査
心電図は、心臓の電気的な活動を記録する検査です。心筋に炎症があると、心筋細胞がダメージを受け、電気信号の伝わり方に異常が生じます。これにより、不整脈や心筋梗塞に似た波形の変化が見られることがあります。ベッドサイドで簡便に行える重要な検査です。

血液検査
血液検査では、体内の炎症の程度を示すCRP値や、心筋細胞が壊れた際に血液中に流れ出るトロポニンTやCKといった酵素の値を測定します。これらの数値が高い場合、心筋炎が強く疑われます。また、原因となるウイルスの抗体価を調べることもあります。
心エコー検査
心エコー検査は、超音波を使って心臓の形や大きさ、壁の動き、ポンプ機能などをリアルタイムで観察する検査です。心筋炎になると、心筋の動きが悪くなったり、心臓が拡大したりすることがあります。心臓の状態を詳細に評価できるため、診断や重症度の判定に不可欠です。
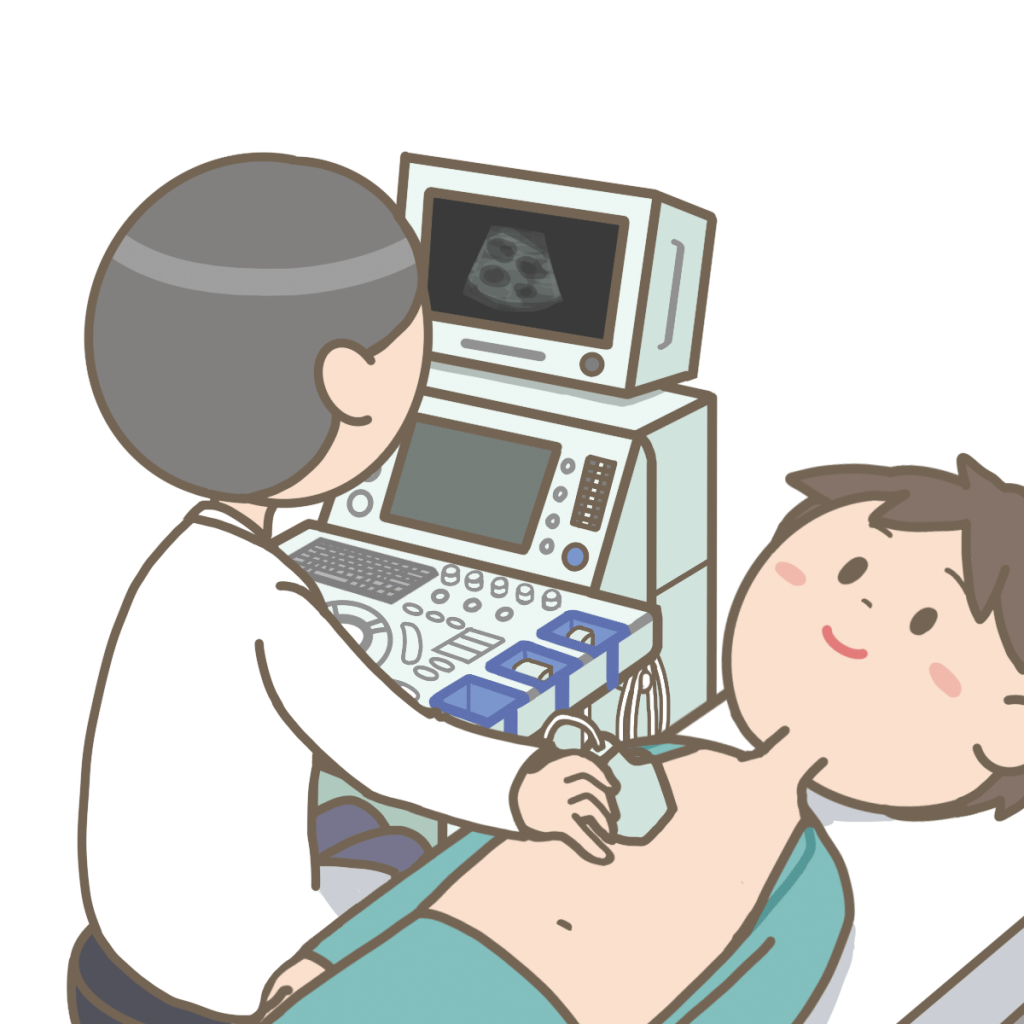
心臓MRI
心臓MRI検査は、心筋の炎症やむくみ、線維化(硬くなること)の状態を画像で詳しく捉えることができる検査です。心筋炎の診断精度を高める上で非常に有用です。特に、炎症が起きている部位や範囲を特定するのに役立ち、治療方針の決定にも影響します。
心筋生検
心筋生検は、カテーテルを使って心臓の筋肉の一部を直接採取し、顕微鏡で調べる検査です。炎症細胞の有無などを直接確認できるため、心筋炎の確定診断に繋がります。ただし、体への負担があるため、他の検査で診断が困難な場合など、必要と判断された時に行われます。
治療法
心筋炎治療の基本は、心臓の負担を減らし、機能を回復させることです。まずは入院による安静が第一です。その上で、症状を和らげる対症療法や、心臓の機能を助ける薬物療法を行います。重症化して命の危険が迫る場合には、より専門的な治療が必要となります。
入院による安静と対症療法
心筋に炎症が起きているときは、心臓に負担をかけないことが最も重要です。そのため、基本的には入院してベッドの上で安静を保つ必要があります。発熱や痛みに対しては解熱鎮痛薬を使用するなど、出現している症状を和らげるための対症療法が行われます。
原因に応じた薬物療法
心臓のポンプ機能が低下している場合は、心臓の負担を軽くする薬(β遮断薬、ACE阻害薬など)や、尿の量を増やしてむくみを取る利尿薬などが使われます。炎症を抑える目的でステロイドや免疫抑制薬が用いられることもあります。原因や病状に応じて適切な薬剤が選択されます。
重症化した場合の補助循環装置
薬物治療だけでは心臓の機能が維持できない劇症型心筋炎などの重症例では、機械で心臓や肺の働きを一時的に代行する補助循環装置(ECMO、IMPELLAやPCPSなど)を使用します。これにより、心臓を休ませ、機能の回復を待つための時間を稼ぐことができます。
心筋炎の経過、予後
心筋炎の治療後の経過は、重症度や受けたダメージの程度によって大きく異なります。多くの場合は後遺症なく社会復帰できますが、一部では心臓の機能が元に戻らず、慢性的な心不全の状態になることもあります。退院後も定期的な通院と自己管理が重要になります。
軽症から中等症の心筋炎
軽症から中等症の心筋炎であれば、適切な治療によって心臓の機能が完全に回復し、後遺症を残さずに治癒することが多い印象です。回復までには数週間から数ヶ月かかることもありますが、その後は通常の生活に戻ることが可能です。ただし、再発のリスクはゼロではありません。
重度の心筋炎
心筋が受けたダメージが大きい場合、炎症が治まった後も心臓のポンプ機能が十分に回復しないことがあります。その結果、拡張型心筋症などの状態に移行し、慢性的な心不全となる可能性があります。この場合、生涯にわたる内服治療や生活習慣の管理が必要になります。
また退院後も医師の指示に従って服薬を続けることが大切です。また、心臓に負担をかける過度な運動や塩分の多い食事は避ける必要があります。定期的に通院し、心エコー検査などで心臓の状態をチェックしてもらいましょう。風邪などをきっかけに再発することもあるため、体調管理が重要です。
お問合せ・ご相談について
患者様
当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。
お問い合わせメールフォームはこちら
| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |
|---|
他施設の方(患者様のご紹介ほか)
地域連携室までご連絡ください。
TEL:047-384-8564
月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30




