異形狭心症
異型狭心症とは
異型狭心症(いけいきょうしんしょう)は、心臓の筋肉に酸素などの栄養を供給する「冠動脈」という血管が、一時的に強く痙攣(けいれん)することで発生する病気です。冠攣縮性狭心症または血管攣縮性狭心症とも呼ばれます。血管が痙攣すると内側が急激に狭くなり、心筋への血流が不足して胸の痛みや圧迫感といった発作が起こります。一般的に知られる労作性狭心症が、体を動かした際に症状が出るのに対し、異型狭心症は主に夜間や早朝など、体を休めている安静時に発作が起こるのが最大の特徴です。
他の狭心症との違い
異型狭心症をより深く理解するために、他の代表的な狭心症である「労作性狭心症」と、特に危険な「不安定狭心症」との違いを知っておくことが重要です。これらは同じ狭心症という名前がついていますが、原因や対処法、緊急性が大きく異なります。
| 異型狭心症 | 労作性狭心症(安定) | 不安定狭心症 | |
| 主な原因 | 冠動脈の痙攣(攣縮) | 動脈硬化による血管の狭窄 | プラーク破綻と血栓形成 |
| 症状が起こるタイミング | 主に安静時(夜間〜早朝) | 主に運動時(心臓に負担がかかった時) | 安静時・運動時を問わず(予測不能) |
| 症状のパターン | 発作的に起こり、数分で治まる | 毎回同じ程度の負荷で起こり、休むと治まる(安定している) | 症状が悪化していく(頻度・時間・強さ) |
| 危険性・緊急性 | 薬でコントロール可能だが、心筋梗塞などを起こすリスクあり | 安定しているが、動脈硬化の進行管理が必要 | 心筋梗塞に移行するリスクが極めて高く緊急の治療が必要 |
異型狭心症の主な症状
主な症状は、突然現れる胸の痛みや圧迫感です。「胸が締め付けられる」「胸に重い石を乗せられたよう」などと表現されることが多く、痛みは胸の中央部から左側にかけて感じることが多いですが、人によっては喉や顎、左肩、腕にまで痛みが広がる(放散痛)こともあります。発作は数分から十数分でおさまるのが一般的ですが、その間は強い不安感を伴うことも少なくありません。冷や汗や息苦しさを感じる場合もあります。
夜間から早朝にかけての胸痛
異型狭心症を強く特徴づけるのが、発作が起こる時間帯です。特に、就寝中や明け方など、リラックスしている状態で症状が現れやすくなっています。これは、体の活動と休息をコントロールする自律神経の働きが関係していると考えられています。副交感神経が優位な状態から、活動的な交感神経が優位になる早朝の時間帯に、冠動脈の攣縮が誘発されやすいことが知られています。日中の活動時には症状が出ないため、見過ごされやすい点も注意が必要です。
数分から十数分続く圧迫感
発作の持続時間は、通常は数分から長くても15分程度で自然に症状が和らいでいきます。発作がおさまると、何事もなかったかのように普段の状態に戻るのが特徴です。しかし、もし胸の痛みが30分以上続く場合や、今まで経験したことのない激しい痛みに襲われた場合は注意が必要です。心筋梗塞の可能性も考えられるため、ただちに救急車を要請するなど、迅速な対応が求められます。
原因
異型狭心症の直接的な原因は、冠動脈が異常に強く収縮する「冠攣縮」です。正常な血管は必要に応じて拡張したり収縮したりしますが、何らかの理由でこの調節機能がうまく働かず、過剰に収縮してしまう状態です。血管の内側を覆う「血管内皮細胞」から放出される血管を拡張させる物質の働きが弱まったり、逆に収縮させる物質が過剰になったりすることが、この異常な痙攣の一因と考えられています。
また根本的な原因は完全には解明されていませんが、冠動脈の機能異常が深く関わっていると考えられています。
以下が冠動脈の痙攣を引き起こす危険因子として知られています。
- 喫煙
- 過度の飲酒
- 精神的なストレス
- 過労
また、遺伝的な要因や、血管内皮細胞の機能低下なども関係すると考えられており、これらの因子が複数重なることで発症リスクが高まります。特に日本人には比較的多い疾患とされています。
検査・診断方法
心電図検査
発作が起きている最中に心電図検査を行うと、特徴的な波形の変化(ST部分の上昇)が記録されます。これは診断において非常に有力な証拠となります。しかし、発作は短時間で終わってしまうため、医療機関を受診したタイミングで都合よく発作が起きているとは限りません。そのため、発作が起きた際に使用する携帯型心電計を貸し出し、自宅で症状が出た時に記録してもらう場合もあります。
ホルター心電図(24時間心電図)
ホルター心電図は、携帯可能な小型の心電計を体に装着し、24時間にわたって日常生活中の心臓の動きを記録する検査です。これにより、本人が自覚していない夜間の発作や、症状と心電図変化の関連性を確認することができます。特に夜間や早朝に症状が出る異型狭心症の診断において、非常に有用な検査方法として広く用いられています。検査中は入浴ができないなどの制限はありますが、痛みなどはありません。
薬で発作を誘発する負荷試験
他の検査で診断が確定しない場合、入院の上で心臓カテーテル検査と同時に薬物負荷試験が行われます。これは、手首や足の付け根の動脈からカテーテルという細い管を心臓の冠動脈まで進め、アセチルコリンなどの薬剤を直接投与して意図的に冠攣縮を誘発する検査です。痙攣が確認できれば、異型狭心症と確定診断されます。専門医の厳重な管理下で安全に行われる、最も確実な診断方法です。
治療法
薬物療法
治療の中心となるのは、冠動脈の痙攣を防ぐための薬物療法です。主に、血管を広げて痙攣を抑える「カルシウム拮抗薬」が第一選択薬として用いられます。また、発作の予防や、起きてしまった発作を鎮める目的で、血管拡張作用のある「硝酸薬」が併用されることもあります。これらの薬は、症状がないからといって自己判断で中断せず、医師の指示通りに毎日きちんと服用し続けることが最も重要です。
舌下錠
急な発作が起きた場合に備えて、頓服薬としてニトログリセリンの舌下錠やスプレーが処方される場合があります。これは、胸に痛みを感じた際に舌の下に含んで溶かすことで、有効成分が速やかに吸収され、数分で冠動脈を広げて症状を和らげます。いつ発作が起きても対応できるよう、常に携帯することが大切です。もし使用しても症状が改善しない場合や、痛みが悪化する場合は、すぐに医療機関に連絡する必要があります。
カテーテル治療
以下のような特定のケースでは、カテーテル治療などが検討されることがあります。
- 動脈硬化による狭窄を合併している場合 異型狭心症の患者さんの中には、血管のけいれんに加え、動脈硬化による血管の狭窄を合併している方もいらっしゃいます。このような場合、狭窄が起きている部分に対してカテーテル治療(ステント)を行い、物理的に血管を広げる治療が有効となることがあります。
- 薬物療法だけでは発作を抑えきれない重症の場合 複数の薬剤を最大限使用しても、命に関わるような重い発作が繰り返し起こるような非常に稀なケースでは、冠動脈の入り口にステントを留置したり、ペースメーカーを植え込んだりする治療が検討されることがあります。
- 心筋梗塞を発症した場合 血管のけいれんが長時間に及んだ結果、血流が完全に途絶えて心筋梗塞を発症してしまった場合には、緊急でカテーテル治療を行い、血流を再開させる必要があります。
日常生活で気をつけるべきこと
まずは禁煙を徹底する
喫煙は冠攣縮を誘発する最大の危険因子であり、治療の妨げとなるため、診断を受けたら直ちに禁煙することが絶対条件です。禁煙するだけで発作の頻度が劇的に減少することも少なくありません。自分の意志だけで禁煙するのが難しい場合は、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることも有効な選択肢です。家族の協力も得ながら、確実に禁煙を達成することが、治療の成功と再発予防への最も確実な道となります。
ストレスを上手に管理する
精神的なストレスや身体的な疲労は、自律神経のバランスを乱し、発作の引き金となりやすいです。そのため、仕事や日常生活において無理をせず、意識的にリラックスする時間を作ることが大切です。趣味に没頭する、軽い運動を取り入れる、ゆっくり入浴するなど、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。また、睡眠不足も大敵ですので、規則正しい生活を心がけ、質の良い睡眠を十分に確保することが求められます。
飲酒や食事内容を見直す
アルコールの過剰摂取は、それ自体が発作を誘発することがありますので、飲酒は控えるか、適量にとどめる必要があります。特に深夜の深酒は避けるべきです。食事については、特定の食品が直接的な原因になることは少ないですが、血管の健康を保つためにバランスの取れた食生活が推奨されます。暴飲暴食を避け、野菜や魚を中心とした食生活を心がけることは、心臓だけでなく全身の健康維持にもつながります。
異型狭心症を放置するリスク
異型狭心症は、発作がおさまれば普段と変わらない状態に戻るため、症状を軽視して放置してしまう人もいます。しかし、適切な治療を受けずにいると、冠動脈の痙攣が長時間に及んだり、完全に血管が詰まってしまったりすることで、命に関わる深刻な状態を引き起こす危険性があります。胸の症状は、体からの重要なサインであると認識し、決して自己判断で放置してはなりません。
- 心筋梗塞に移行する危険性:冠動脈の痙攣が非常に強く、長時間にわたって続いてしまうと、心臓の筋肉への血流が完全に途絶え、筋肉が壊死してしまう心筋梗塞に移行することがあります。
- 危険な不整脈(心臓突然死)の可能性:発作によって心筋への血流が一時的に途絶えると、心臓の電気的な活動が不安定になり、致死性の不整脈(心室細動など)が誘発されることがあります。この不整脈が起こると、心臓はポンプとしての機能を失い、数分で意識を失い、死に至る危険性があります。
お問合せ・ご相談について
患者様
当院循環器内科外来にお越しいただくか、無料メール相談(問い合わせメールフォーム)をご利用ください。
お問い合わせメールフォームはこちら
| 循環器内科外来 | 月曜日~土曜日(祝日除く) |
|---|
他施設の方(患者様のご紹介ほか)
地域連携室までご連絡ください。
TEL:047-384-8564
月~金曜日 8:30-17:00/土曜日 8:30-12:30
この記事を書いた医師
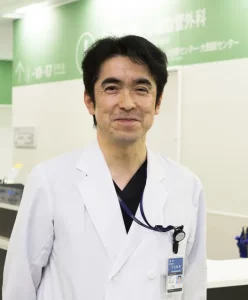
倉持 雄彦(くらもち たけひこ)
千葉西総合病院 副院長
循環器内科主任部長




